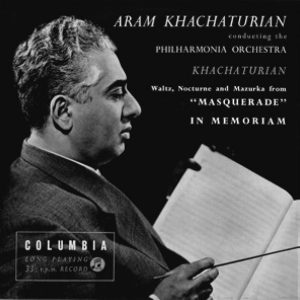プーシキンが『青銅の騎士』に詠い、ゴーコリがネフスキー大通りを讃え、ドストエフスキーがその虚構を見抜いたピョートル大帝の夢の都、サンクト・ペテルブルクは、およそ300年前に突如として作られた人工の都でした。
ロシア帝国の首都となったペテルブルクには宮廷文化が花開き、プーシキン、ドストエフスキーをはじめとする多くの文人、チャイコフスキーをはじめとして、リムスキー=コルサコフ、ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチと続く多くの音楽的才能を輩出しました。
しかし、20世紀に入るとペテルブルクは多くの災厄──まるで、プーシキンが描いたネヴァ河の氾濫のように──を蒙ることになります。第1次世界大戦によるペトログラードヘの改名とそれに続く革命。モスクワヘの再遷都。レニングラードへの再びの改名と第2次世界大戦におけるドイツ軍との1年以上におよぶ市街戦など。
これらの災厄によって、一時は隆盛を誇ったペテルブルクの音楽文化も次第に力を失っていきます。よく知られたピアニスト、ソフロニツキー、ユーディナ、それに作曲家でもあったショスタコーヴィチなどは、ペテルブルクで教育を受けながらも、モスクワで活躍した音楽家でした。
このような中、レニングラード(ペテルブルク)
1人は、50余年に亘ってレニングラード・フィルの常任指揮者を務めたエフゲニー・ムラヴィンスキーです。ムラヴィンスキーは亡くなるまで常任指揮者の地位に留まり、このオーケストラをロシア随一、いやむしろ世界有数のオーケストラヘと育て上げました。
もう1人は、モスクワの俊英を尻目に、若干16歳でチャイコフスキー・コンクールを制したピアニスト、グリゴリー・ソコロフです。モスクワの音楽筋、審査員、それに有力な出場者の誰もが──おそらく本人ですら──このレニングラードからやってきた若者が、難物の協奏曲2曲(チャイコフスキーの第1番と、いくつかの技巧的なものから選んだもう1曲──この時はおそらくサン=サーンスの第2番)
この年の全く離れた2人の天才──このような才能を前にして他に浮かぶ言葉がないのです──に共通する点は、生まれた街、レニングラードヘの強固な結び付きです。
ムラヴィンスキーもソコロフもレニングラードを離れることを好まず、ムラヴィンスキーは国外はもとより、おそらく魅力的な提案があったであろうモスクワにすらほとんど関心を抱かず、終生レニングラードに暮らしました。
一方のソコロフはさらに先鋭的で、モスクワを訪れたのは、チャイコフスキー・コンクールの時ただ一度で、その後は、現在までを含めて(現在はドイツで暮らしているようです)
およそ上からの命令が絶大であったソ連時代に、これほど徹底してモスクワを避けた──あるいはレニングラードを離れなかった理由とは一体何だったのでしょうか。
私はそこに、他とはかけ離れた2人の個性と同時に、大地に根ざした伝統都市モスクワを嫌い、西洋を目指して造られた人工都市サンクトペテルブルクの、美しさと幻影に満ちた矛盾と同質の何かを感じてしまうのです。
このようにお前は深淵の眞際に、
高いところに、その鐵の馬勒をもって
ロシヤを後足で立たしたのではなかったか?
&nnsp;