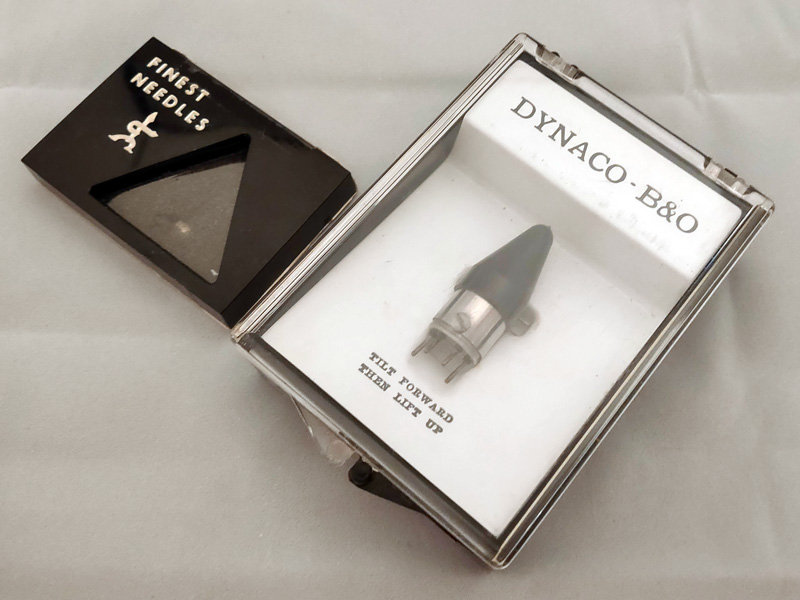初期盤を再生するときに、避けて通ることの出来ない問題の一つがイコライザーカーブです。
現在市販されているプリアンプやフォノイコライザーアンプのイコライザーカーブ(Phono入力の特性)は、ほぼ全てにおいてRIAAカーブが採用されています。その理由はごく単純で、現在入手可能なレコードのほとんど全てがRIAAカーブ特性で制作されているからです。しかし、これらのRIAAカーブが搭載されたアンプで、いわゆる初期盤を再生してみますと、高域が強調された音であったり、低音がもたついて聴こえたり、ということが往々にして起こります。
そもそも、「RIAAカーブ」と呼ばれるイコライザー特性は1952年にRCAが「NEW ORTHOPHONICカーブ」として発表し、1953年にはRIAA(Record Industry Association of America)がその特性を追認する形で標準化したものです。つまり、少なくとも1953年以前のレコードは(実際には50年代末頃までは)、各社さまざまなイコライザーカーブを使用してレコードを製作していたということになります。
RIAA以前の主なイコライザーカーブには、コロンビアカーブ、NABカーブ、AESカーブ、デッカffrrカーブ、RCAカーブ、British-LPカーブなどがあります。これらは、コロンビアカーブとNABカーブがかなり近い特性であることを除けば、それぞれに異った特性を有しており、実際それらのカーブグラフを眺めてみても誤差として看過できるような差ではないように思います。
とはいえ、これらの初期盤をRIAAカーブで再生しても大きな音の破綻が起きるわけではありませんし、トーンコントロールを使えば相応に元のイコライザーカーブへ近づけることも可能です。それにも関わらず、イコライザーカーブを合わせて(実際には、採用しているカーブを明記しているレコードは少なく、カッティング工場やプレス年代、レーベル、そして最後には聴いた音から類推するより他ないのですが)聴く初期盤は、フォーカスが見事に収斂して、音楽が浮かび上がるように躍動して聴こえてきます。
初期盤コレクターの方々であればすでにご承知でしょうが、その昔、評論家が酷評したような初期盤などの中にも素晴らしい演奏が多々あります。これなどは、RIAAカーブの再生によって聴かれた、半ば間違った前提によって成された評論であったと考えるのは、少し好意的に過ぎるでしょうか。
*
例によって前置きが長くなってしまいましたが、このアンプは、各社のイコライザーカーブに対応した管球式の可変型イコライザーアンプです。イコライザー部の他にセレクターとボリュームを取り付けてあるため、パッシブ型の簡易プリアンプとしても使用可能です。
イコライザー部は、ロールオフ(高域減衰)には、音抜けの良いCR型フィルターを、ターンオーバー(低域増幅)には、力感の出るNF型フィルターを使った、CR-NF型フィルターを採用しています。使用真空管は初段、2段目に6072A/12AY7を使い、初段と2段目の間にCRフィルターを挟んでいます。2段目の後にNFフィルターが入り、3段目の6463で増幅後にライントランスが入り、セレクター、ボリュームを経由してプリアウトとなる構成です。
ロールオフとターンオーバーはそれぞれに独立しており、いずれもフラットのポジションが設けてあるため、LP、78回転SPを含めたほぼ全てのイコライザーカーブが再現可能です。また、ターンオーバーには別に低域上昇限度(ブースト量)の設定が可能なため、デッカカーブやコロンビアカーブのように低域上昇限度の設けてあるカーブも正確に再現することが可能です。
使用部品はMILスペックのものを中心に音質、信頼性の高いものを選んでおり、全て手配線によって作られています。電源部は、オーバースペックと思えるような大型のオイルコンデンサーと、リップルフィルターによって平滑してあり、電源起因のノイズはほぼ認識できなレベルとなっています。
このアンプは、以前当店でオーダーメイドにて販売していたもので、ご購入されたお客様のグレードアップに伴って里帰りしてきたものです。ワンオーナー品であり、各数値も問題はありませんでした。むしろエージングが進んで程よい状態になっているのではないかとも思います。
音については最小限の音作りで精緻、すなわちモニターサウンドに近い印象を受けますが、販売側の評価を書いたところで大した参考にはならないと思いますので割愛させていただきます。店頭での試聴が可能です。
Roll-off
1.59KHz(表記は1.5KHz)Columbia/ NAB/HMV
2.12KHz(表記は2.1KHz)RIAA
2.5KHz AES/RCA等
3.0KHz Decca/CCIR
12KHz SP(フィルター)
Turn-over
300Hz SP
400Hz AES/CCIR
500Hz RIAA/Columbia/NAB/Decca/HMV
630Hz RCA-EP
800Hz RCA
Turn-over boost
6dB SP
12dB Decca
14dB Columbia
16dB(表記なし) NAB
20dB RIAA/RCA/AES
サイズ W285 × H160 × D400mm
重量 約5kg
消費電力 約30W