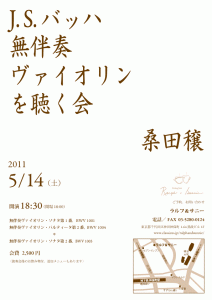昨日facebookの投稿で知ったのですが、ピアニストのアレクセイ・リュビモフがモスクワで行ったコンサートの前半で、ウクライナの作曲家シルヴェストロフの作品を弾いたところ、後半になって警官が闖入してコンサートを中止させたのだそうです。
ウクライナの惨状を思えば、モスクワでコンサートができている、それだけでも過分に過ぎることなのかもしれませんが、それにしても時の権力が芸術活動にこれほどあからさまな干渉をしてきたことに底知れぬ怖ろしさを感じるとともに、その横暴にはただただ呆れ果てるばかりです。
動画を見ますと、シューベルトの即興曲第1番の冒頭で警官が中止を叫んで聴衆が帰りかけますが、リュビモフは演奏を続け、警官の制止と監視の中第2番を最後まで弾ききり、万雷の拍手を浴びている様子が見て取れます。
外面的な事実を追えば、たった2人の警官によって(その裏には幾千幾万の権力の追従者がうごめいているのでしょうが)
音楽という芸術は、カントがいみじくも「熟考するためのものを何も残さない」と言ったように、言語化できないという意味において、何か主義主張を表明することは難しく、故に政治活動、反体制運動などを実効的に行うことも困難です。それは、ソ連時代、マヤコフスキーやメイエルホリド、ミホエルスといった物言う芸術家が次々と粛清されていく中、音楽家はおそらくただの一人も粛清されなかったことからも、権力者から見た音楽芸術の立ち位置を推し量ることができます。
それにも関わらず、音楽芸術は人間が生活していく上において必要不可欠な何か、「精神性」とでも呼ぶべきものを備えており、その「精神性」は物言わぬ形で我々に影響を与え、権力側ばかりではなく、反権力の側にもさまざまなものを訴えかけているように思えるのです。
かねてよりクラシック、それも〝レコード芸術〟界隈では、「精神性」という言葉がしきりと使われてきました。かの吉田秀和は「フルトヴェングラーには精神性がある」と言い、宇野功芳は「カラヤンには精神性が無い」と言うのがある種の決まり文句でした。これら評論家先生の名前を出すだけで「精神性」の流行した時代が分かろうというものですが、幸か不幸かその時代がいわゆる〝レコード芸術〟の全盛期と重なったこともあり「精神性」なる言葉は不必要に濫用されてしまうことになります。
残念ながら流行には反動がつきもので、カラヤンを皮切りとして、クライバー、アバドからラトルやドゥダメルへと至る指揮者達の時代に「精神性」という表現はほとんど使われることはなくなりました。対照的にフルトヴェングラーらいわゆる「精神性」時代の指揮者たちは「録音の悪い、古臭い」演奏とされ、今や「精神性ある演奏」は悪い音や情けない演奏を褒めるための慣用句とさえ言われる始末です。
たしかにここで使われている「精神性」という言葉は、端的に言ってしまえば賛美や批判のための道具、それも言葉の定義が曖昧なことによって反論の焦点すらぼやかしてしまうような、まことに都合のよい道具として使われていたように思えます。
では本来の意味での「精神性」とは何か、ということになるとこれは極めて難しい問題となります。カントの芸術論やニーチェの『悲劇の誕生』あたりが足掛かりとはなるのでしょうが、広大無辺な芸術論の中に含まれる概念の一つであると考えられることからも、私ごときが定義どころか議論することすらためらわれるような代物といえます。
とは言え、あれやこれやの書籍をつまみ食いしながら私なりの理解をもって言えることは「芸術とはすなわち精神活動に他ならない」ということです。アリストテレスが「知性や思考がなければ実践(表現)
アリストテレスはポイエーシス(創造)