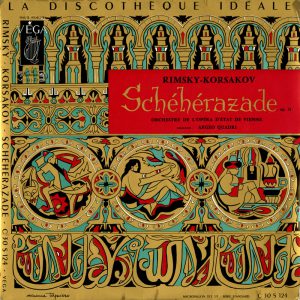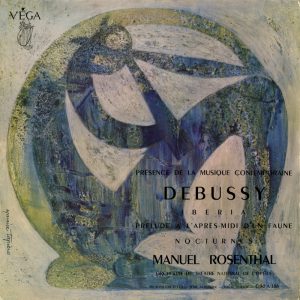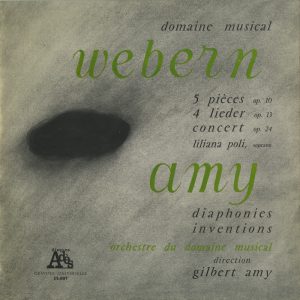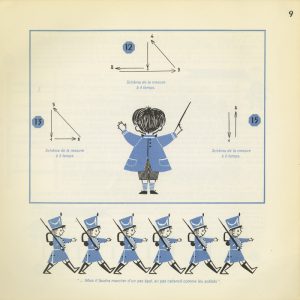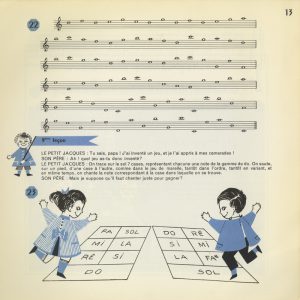前回、「いい音」の基準として「原音≠マスターテープの音」というものが提唱されたものの、その定義は些か曖昧であるという趣旨のことを書きました。
では、なぜ「原音」の定義が曖昧になってしまうのかと考えますと、それは音や音楽の良し悪しを最終的に判断するのが、結局は人であるからではないでしょうか。
人の主観によって聴かれた音は、あくまでもその人の感じた音であり、絶対的な基準とはなり得ません。今横に居る人と自分が見ている空の青い色が同じ、あるいは違う青であることの証明は誰にもできないのと同じように、同じ場所で同じ(はずの)
また、たとえ「私」が同じ環境で同じ音楽を聴いたとしても、今日の「私」が聴く音と明日の「私」が聴く音は違って聴こえるでしょうし、10年前の「私」が聴いた音とも違うことでしょう。
結局、人という不確定的な要素を対象とした芸術なり美術というものに絶対的なものは存在せず、鑑賞者という媒体を通して相対的にのみ評価されるものなのではないでしょうか。
もし、これら芸術や美術が絶対的といわれるものに僅かでも近づく可能性があるとすれば、それは長い歴史によって磨き上げられ、淘汰、選別が繰り返された末になることでしょう。
このように考えますと、原音であるとかマスターテープの音といったものは、確かに「いい音」のある面は写しとっているのかもしれませんが、「いい音」全体の物差しとするには些か役不足である感は否めません。
しかし、役不足という言葉は、あらゆる「いい音」の表現に対しても当てはまることですから、「いい音」の全体像を探し当てるためには「いい音」の断片を積み重ねて、全体像を構築していく他ないようにも思えるのです。
それはさておき、私の考える「いい音」は、「音楽的な体験、感動の伝わる音」という何とも観念的なものです。再生音というものは、再生装置や環境によって面白いように変化しますが、ある程度の水準で再生されれば、その録音の底流を流れている「体験や感動」は感じ取ることが出来るように思うのです。
レコードやCDなどの再生媒体は、演奏が行われたその場に居なかった人々へ、能うかぎりその内容を伝えるための手段ですから、たとえ音響特性の優れた音でその演奏を録音/再生できたとしても、その場の体験、感動を多少なりとも伝えることができなければ、その録音/再生は成功したとは言い難いように思えるのです。